杉の木から、数ヶ月をかけて生み出される茶箱。
店で、家で、長く愛される伝統の保存容器には、
昔ながらの、初期人の手仕事が息づいている。

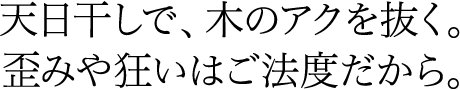
天日干しで、木のアクを抜く。
歪みや狂いはご法度だから。
呉服町。鍛冶町。紺屋町。大工町。
名前を聞けば、古くからその町に暮らす人たちの生業がわかる。
静岡県藤枝市の茶町も、そんな町のひとつ。
今も昔も茶問屋の集まる地域の一角に、土屋製函所の工場がある。
「函」は「箱」。製函所という社名も、町の名と同じく、シンプルで明快だ。
土屋製函所は、茶を出荷する際に入れる箱、茶箱を作るメーカー。
創業は昭和24年。初代は、現当主・土屋恵司さんの父である。
「もともとは板金を主にやっていて、茶箱作りは、よそのを手伝っていた。
それを自分のところで請け負うようになったのが、昭和24年ごろ。
古いほうの建物も、その頃に建てたものです」
だからもうボロボロで、と土屋さんは笑う。
が、必要な箇所は補強され、設備には手が加えられており、
何より整頓されていて、明るく清潔だ。
動線がクリアで、作業がしやすそうな環境に整えられているのは
はじめて訪れた人間にも、一目で見て取れる。

茶箱は、極めてシンプルな箱である。
杉板を波釘で継ぎ、それを箱型に組んで、
中にトタンの板を敷いて溶接し、外周に目張り用の和紙を貼る。
5キロ、10キロ、20キロ、40キロという呼び名は、
中に入る茶の量を示したものであるとのこと。
運搬用の箱として、まず軽く扱いやすいこと。
そして、保存容器として、湿気や虫害から保護する機能を備えていること。
製造工程は、この2点をかなえるための、必要十分な作業である。
まずは、板の準備。
「素材を作る」ところから、すべてが始まる。
素材は、国産の杉。
「ヒノキは硬くていい材料だけど、匂いが強すぎる。
中に入れるものに影響するのでね。
板の厚みは10ミリ。6尺の丸太を、製材所でだいたい8枚から10枚にしてもらって、
1カ月半くらいかけて天日干しにします」
雨の日も、基本的には「このまんま。置きっぱなし」であるという。
「木は、濡れなきゃアクが抜けない。
アクの抜けない木は、いくら干してもボトボトしている。
きれいに乾燥しないから、板も軽くならないし、
製品になったあとで、歪みや狂いが出るんです」
雨を当て、風を当て、板が十分に干されたら、次は「木取り」。
ここでやっと、木が、工場に持ち込まれる。
「外から来た人は、『木の匂いがする』って言うよね。
我々はもう、慢性だからわからないけど」
長さを揃え、切る作業は、かつては鋸で行われていたが、
今は電動の丸鋸で行われる。

切った板は、すぐには組み上げに使わない。
ここでもう一度、水を通すのだ。
曰く「暴れさせる」作業は、板を落ち着かせるためにどうしても必要な工程だという。
「早く使うと、どうしても戻りたがるでね。
板は、呼吸してますから」
重ねて寝かせること、さらに2カ月。
完全に落ち着いた板の表面を削り、
波釘で接いで、必要な幅にする。
削るのは、箱の外側に出る片面のみ。
「それ以上に、手間はかけられんのでね」
それもまた、茶箱という用途にふさわしい簡潔さ。
このあと、削った木を、さらに作る箱に必要なサイズに切り揃え、
やっと箱の素材が出来上がる。
